番組表
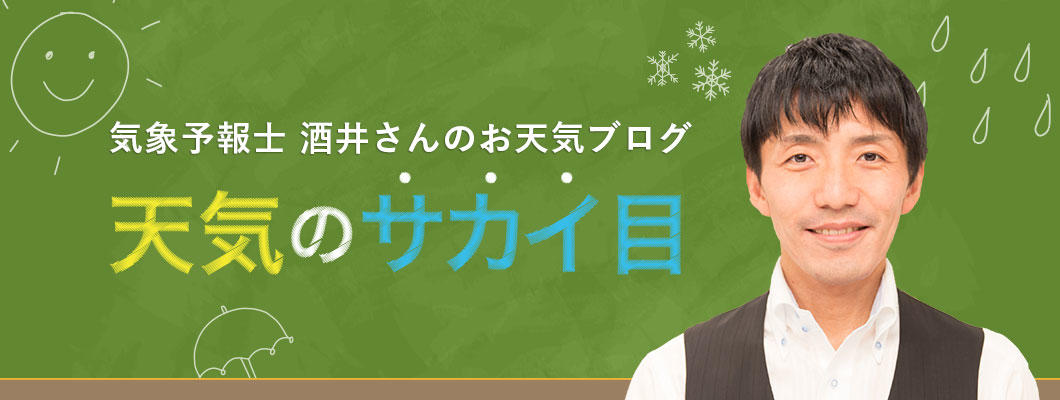
寒波の最中に 2018年02月14日
先週にかけて、今シーズン1番の寒気が九州に入っていて、今朝もかなり冷え込みましたが、日中になってようやく暖かくなりました。
待ち望んでいた春の暖かさはこのあともしばらく続きそうです。
さて、寒波の最中に視聴者の方から、「寒い朝同じ気温で車のフロントガラスが凍る日と凍らない日があるのはなぜですか?」との質問があったので、いろいろと考えていました。
気温以外に考えられる要素は、まずは「湿度」。
空気中の水蒸気が多い方が水滴や氷の粒が発生しやすい、というのはなんとなくイメージがつきますね。
次に「夜間の天気」。
雲もなく晴れていると、放射冷却の効果が強まって地上付近の熱が上空へと逃げるため、気温は下がりやすくなります。
このときに風が弱いと、空気がかき混ぜられずに冷たい空気がどんどん地上にたまっていくため、冷却効果がさらに強まります。
また、1月半ば以降になると日の出の時刻が次第に早くなっていきます。
太陽が顔を出すとすぐに気温が上がっていくため、同じ最低気温を観測した日でも、日の出の時刻が遅い1月半ばまでの時期の方が冷える時間は長くなります。
このため、「時期」も1つの要素となりますね。
そしてもう1つ考えたのが、「フロントガラスの状態」。
雨や雪は大気中のちりや火山灰などの微粒子を核にして成長するため、核となりえる物質がフロントガラスにある状態、つまりほこりなどがたまっている状態の方がフロントガラスの霜や氷が成長しやすいのではないかと思います。
ということで、「フロントガラス仮説」を自分の車で実験。
宮崎市では、2月5日から7日にかけて氷点下まで冷え込む予想だったので、前日のうちにフロントガラスの半分(運転席側)だけをキレイに拭いて準備しておきました。
この3日間の記録はこのようになっています。
<2月5日>
夜遅くに-1.1度の最低気温を記録したものの、朝は0度前後だったため、フロントガラスは一切凍らず、写真を撮るまでもない状態。
<2月6日>
未明頃に-2.8度を記録し、気温としては十分な低さ。
7時40分撮影の写真では、前日の夜に汚れをふき取ったものの乾拭きをしていなかったせいか、フロントガラスの左側には氷の筋が多数発生。
ただ、霜の結晶をよく見ると、放置していた右側は1つ1つの結晶が大きいのに対して、掃除した左側は結晶が小さくなっています。
しっかり乾拭きをしておけば、左右ではっきりと違いが出そうな予感。
<2月7日>
明け方に-2.0度を記録したものの、前日より若干風は強め。
7時ごろに撮影したところ、それほど霜は発生していない状態。
とはいえ、乾拭きが十分ではなかった中央の筋を除けば、右側で霜が点々と発生している一方で、左側にはほとんど霜が出来ていないように見えます。
昨日の気象条件のときにしっかりと乾拭きができていれば、もっとはっきり霜の成長の違いが観察できたと思うので、ちょっと残念です。
はっきりと分かりやすい結果が撮れるまでこの実験を続けるつもりですが、今シーズンは強烈な寒波が来ないことを祈って、実験の続きは年末以降にします。



